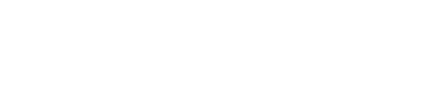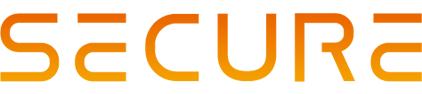共連れ対策3選!入退室管理の認証方法・事例も紹介

「共連れ」とは、1人分の認証で複数人が一緒に入室してしまう行為を指します。情報漏洩や不正アクセスのリスクを高め、事件・事故発生時の事後検証を困難にする要因にもなります。
本記事では、共連れリスクを最小化する3つの対策や入退室管理システムの認証方法、共連れ対策に成功した企業の事例も紹介します。
自社の状況に合わせてどのように「共連れリスク」を最小化できるか、どの方法が自社に適しているかを判断でき、実践的なセキュリティ対策の検討が可能です。
なお、共連れ対策なら株式会社セキュアが提供する「SECURE AC」入退室管理システムがおすすめです。
入室・ 退室ごとにログを正確に記録するので、「誰が・いつ・どこにいたのか」を把握でき、権限を持たない外部者の侵入や情報漏洩リスクの大幅な軽減が期待できます。
顔・指紋・カード・テンキーと用途に合わせた多様な認証デバイスを取り揃えて、お客様の課題に柔軟に対応できる「SECURE AC」入退室管理システムについての詳細は下記からご覧ください。
共連れとは?複数人が出入りするリスク

「共連れ」とは、主にセキュリティの分野で使われる言葉で、入室許可を持つ人がドアやゲートを開けた際に、許可を持たない人が一緒に入室する行為を指します。
本来、入室が制限されている区画・部屋への入室には、生体認証やICカードによる認証が必要です。しかし、「認証を受けた人の意図的な誘導」や「認証を受けた人の後から駆け込む」ことで、不正に入室できてしまうことがあります。
このように正規な認証を経ずに、制限区画に入り込むことを「共連れ入室」と呼びます。共連れ入室を許してしまうと、セキュリティの確保ができず、情報漏洩や不正アクセスのリスクを高めます。
それだけでなく、事件・事故が発生した際に事後検証が困難になることも少なくありません。
そのため、企業や施設では厳重なリスク軽減策が求められます。次の章で共連れを防止する3つの方法を紹介いたします。
共連れ対策に有効な3つの方法

共連れ対策として代表的な方法は、大きく次の3つです。
一つずつ特徴をみていきましょう。
方法1.セキュリティゲートで物理的に共連れを防ぐ
セキュリティゲートとは、認証を通過した人だけが物理的に入室できるように制限する設備です。

IDカード認証や生体認証などで本人照合を行い、通行を許可するエントランスゲートで、下記のような効果が見込めます。
- 物理的に1人ずつの通行を強制できる
- ゲートの高さや設計により不正侵入の難易度が高い
- 入退室履歴と連動でき、証跡管理にも有効
なお、セキュリティゲートには、さまざまな種類があります。ここではセキュアが取り扱っているセキュリティゲートを例に紹介しますので、参考にご覧ください。
| 種類 | 特徴 | 主な設置場所 |
|---|---|---|
| エンターゲート | ・1通路あたり通常25人/分、最大50人/分(入退室管理機器による) ・安全性に配慮した屋外用セキュリティゲート ・屋外または屋内外をつなぐ箇所などへの設置が可能な「防水/防塵性能」に優れている ・不正な通行は検知し、扉(フラップ)を閉じて通行を抑止 ・強引な通行には、ブザーや出力信号に異常を連絡・対応 | ・工場構内・大学キャンパスの出入口・屋外イベント・公共施設のエントランス など |
| スターンゲート | ・1通路あたり通常25人/分、自動ドアモードの場合50人/分 ・フラップ高と通路幅を自由に組み合わせ可能 ・高いセキュリティ性と省スペースを両立 | ・オフィスビルのエントランス・来訪者受付前 など |
| ライトゲート | ・1通路あたり通常25人/分、自動ドアモードの場合50人/分 ・ユニバーサルデザイン・安全性を考慮したフラップ ・省スペース設計(場所をとらないコンパクトデザイン) | ・商業施設や病院のロビー ・バリアフリー通路 など ・シンプルなデザインのため博物館、美術館など文化施設の入口にも適している |
| フレックスゲート | ・1通路あたり通常25人/分、最大50人/分(入退室管理機器による) ・省スペース設計 ・補助ゲートとして利用可能 ・スムーズな通行を実現 | ・オフィスビルの執務エリア入口 ・研究施設内の区画仕切り ・第2・第3のセキュリティゲートとして ・来訪者エリアと社員エリアの間 など |
| サークルゲート | ・最大6人/分 ※連続通行時(入退管理システムの性能に準拠) ・共連れや飛越えを徹底的に排除 ・最高レベルのセキュリティ ・2枚のドアで1人ずつ通行 | ・サーバールーム・電算室などの最重要エリア など |
方法2.アンチパスバックで不正を検出・抑止
アンチパスバックとは入退室管理設備の機能で、入室のID認証の記録がないと退室を許可しない入退室管理システムの仕組みです。

例えば、共連れで不正入室した人は「入室履歴」が記録されていないため、退室時にエラーとなり、不正が判明します。
アンチパスバックを設定することで、下記のような効果があります。
- 入退室履歴の矛盾から、共連れの兆候を把握できる場合がある
- 入退室履歴が正確に管理できる
- 多くの入退室管理システムに標準搭載されている場合が多く、追加機器が不要
なお、アンチパスバックは入室、退室ともに共連れで通過すること自体を防止するのではありません。心理的な抑止力として活用するか、ID認証による入退室ルールを徹底させる程度の目的としての位置付けです。
方法3.監視カメラで行動を記録し抑止力を高める
監視カメラとは、出入口や通路などに設置して、映像によって人の動きを記録・監視する手段です。

防犯対策としてはもちろん、共連れを含む不審な動きを後から確認・検証する手段としても有効です。他にも下記のような効果が見込めます。
- 抑止効果が高く、行動の記録が証拠になる
- 他の方法では検知できないグレーな行動も把握できる
- アンチパスバックと組み合わせることで、共連れ入室の証拠はほぼ確実にとらえられる
アンチパスバックと併用することで、不正入室の抑止力を高め、共連れの証拠をほぼ確実に取得できます。また、画像解析による人数カウントの精度向上とアラームの確実な通知に向けて、環境要因への対策を継続的に行うことが重要です。
なお、「顔認証」とアンチパスバックを組み合わせることで、不正入室対策の精度向上を図る取り組みも行われています。個人を特定する精度の高い認証と、通過ルールの徹底によって、より強固な入退室管理を実現できます。
| 【顔認証 × アンチパスバックで、なりすましと共連れを同時に抑止!】 ・顔認証によって本人確認を確実に行い、アンチパスバックで通過ルールを強制することで、不正な入室行為を大幅に抑止可能 ・さらに入退室ログも自動で記録され、管理の手間も削減できる |
共連れリスクを抑える入退室管理システム4つの認証方法

共連れリスクを最小化するには、運用に合った認証方式を選ぶことが重要です。ここでは、入退室管理システムの認証方法を4つ紹介します。
| 認証方法 | 特徴 |
|---|---|
| テンキー(暗証番号) | ・特定の数字コードを入力することで扉を解錠する認証方法 ・システムトラブルや通信障害の影響を受けにくい |
| ICカード | ・認証用のICチップが埋め込まれているカードで、使用者はカードをリーダーにかざすだけで簡単に認証できる方法 ・比較的安価で導入しやすい |
| スマートフォン | ・Bluetoothや専用のアプリをインストールしてスマートフォンを用いて行う方法 ・会社支給のスマートフォンを有効活用することで、導入コストを抑えられる |
| 生体認証 | ・指紋・顔・静脈などの個人の生体情報を用いて認証する方法 ・偽造や盗難のリスクが極めて低いため、高いセキュリティレベルを実現できる |
なお、入退室管理システムの認証の詳細や導入する際のポイントなどを下記の記事でまとめているので、併せてご覧ください。
共連れ防止につながる施策事例|京都産業大学様

本章では、セキュアの入退室管理ソリューションを導入し、セキュリティ強化を図った企業の取り組み事例を紹介します。
2024年4月、京都産業大学様は新たに男女共用の学生寮「本山寮」を開設しました。
寮運営にあたり、セキュアの顔認証による入退室管理システム(BioStar2)※と在室管理機能(SECURE Platform)を導入しました。加えて、共連れ防止に効果的なアンチパスバック機能を活用し、寮内のセキュリティ強化を図っています。
※ ©2025 Suprema Inc. ここに記載されているBioStar2は、Suprema Inc. の登録商標です
| 導入の目的 | ・男女共用寮における高度なセキュリティ体制の構築 ・学生証の紛失・未所持による認証トラブルの解消 ・共連れによる不正入室の抑止 ・在室状況の正確な把握と、管理業務の効率化 |
|---|---|
| 導入後の効果 | 顔認証による確実な個人識別により、学生証を持ち歩く必要がなく利便性が向上 ・アンチパスバック機能により、共連れで入室した学生の退室をブロックし、不正を可視化 ・入室記録と照合して在室状況をリアルタイムで把握でき、門限管理にも対応 ・顔写真の一括登録によって、導入時の作業負担を大幅に削減 ・保護者や受験生からも高い安心感と信頼を獲得 |
京都産業大学様は、顔認証システムの導入により、学生寮のセキュリティを大幅に向上させました。高い認証精度と利便性に加え、アンチパスバック機能による共連れ防止効果も発揮しています。
この事例は、学生寮だけでなく、高度なセキュリティと利便性が求められるさまざまな施設において、顔認証システムが有効な共連れ防止策となることを示しているといえるでしょう。
本事例の詳細は下記の記事をご覧ください。
ハイレベルなセキュリティと運営の利便性を両立できる顔認証|京都産業大学様
入退室管理システムでセキュリティ体制を強化しよう!

共連れは、正規の認証を受けていない人物が他人に便乗して入室する行為であり、企業や施設の情報漏洩や不正行為の要因になります。共連れを防止するためには、セキュリティゲート・アンチパスバック・監視カメラの3つの方法が有効です。
なお、セキュリティソリューションの導入社数11,000社を超える株式会社セキュアでは、カードリーダーや顔認証、マスク検知などの幅広い認証機能や他社とのシステム連携を含めたセキュリティソリューション「SECURE AC」入退室管理システムを提供しています。
中でも顔認証技術は、ライセンス・デバイス合わせて8,800件以上の導入実績をもち、世界最高クラスの性能を誇ります。
目・鼻・口の特徴点や顔の凹凸などから本人を特定できるのが特徴で、認証済みの本人以外が通行する「共連れ」行為を未然に防ぐことが可能な「セキュアの入退室管理ソリューション」について、総合カタログを配布しています。詳細は下記をクリックのうえ、ダウンロードしてご覧ください。
また、共連れをはじめとした入退室管理システムについてのご相談は、下記からお気軽にお問い合わせください。

セキュリティマーケター
和田 麗奈
保有資格:防犯設備士
株式会社セキュアに入社後4年間、セキュリティソリューション営業に従事。多岐にわたる業界・業種の課題解決に貢献する。
現在はマーケティングチームに所属し、現場での経験を活かしながら活動中。