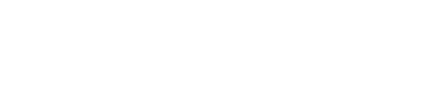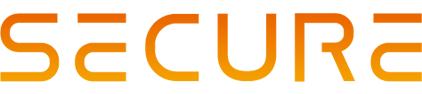内部不正を防ぐには?対策の基本的な考え方とソリューションを解説

企業における内部不正は経営に大きな打撃を与える深刻な問題となっています。情報漏洩や資産の持ち出し、金銭の着服など、内部不正による被害は後を絶ちません。
昨今、銀行や大手企業での内部不正インシデントがニュースになり、既にセキュリティ対策を導入済みの企業であっても、システムの陳腐化や運用の甘さが指摘されています。
内部不正は、一度発生すれば現金の着服といった直接的な損失はもちろんのこと、企業イメージの悪化による信用失墜、それに伴う売上の減少という取り返しのつかない事態にまで発展することも少なくありません。
このような内部不正は、対策をしていなければよりリスクが高まります。
しかし、適切な対策を講じることで、内部不正のリスクを大きく低減することは可能です。本記事では、内部不正の現状やよくある手口、そして内部不正対策のガイドラインに基づく基本的な対策方法を、入退室管理システムや監視カメラなどの物理的セキュリティ対策と合わせて、具体的な事例とともに解説します。
株式会社セキュアでは、企業の内部不正対策にも効果的な入退室管理システム「SECURE AC」、監視カメラシステム「SECURE VS」を提供しています。内部不正対策を検討中の方は、お気軽に下記よりお問い合わせください。
目次
内部不正とは?
内部不正とは、従業員や委託先など、組織内部の人間が意図的に引き起こす不正行為の総称です。
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が公表している「組織における内部不正防止ガイドライン」では内部不正を次のように定義しています。
| 本ガイドラインでは、違法行為だけでなく、情報セキュリティに関する内部規程違反等の違法とまではいえない不正行為も内部不正に含めます。内部不正の行為としては、重要情報や情報システム等の情報資産の窃取、持ち出し、漏えい、消去・破壊等を対象とします。また、内部者が退職後に在職中に得ていた情報を漏えいする行為等についても、内部不正として取り扱います。 |
具体的には以下のような行為が内部不正に該当します。
- 機密情報の外部への持ち出しや漏洩(印刷して持ち歩いたり、USBメモリなどにコピーして持ち出すなど)
- 会社資産の窃取(金銭、物品)
- 他者へのなりすましによる不正アクセス
- 業務データの改ざんや破壊
内部不正の現状
IPAの「情報セキュリティ10大脅威 2025」によれば、2024年に社会的影響が大きい情報セキュリティリスクの中で「内部不正による情報漏洩」が大きな問題として挙げられています※。
実際、2024年には、銀行職員がスペアキーを利用して貸金庫から顧客の資産を持ち出していた事件が発覚し、大きなニュースとなりました。このように、企業における内部不正の手口は高度化・巧妙化しているのが現状です。
※参考:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA), 情報セキュリティ10大脅威 2025
内部不正で企業が被る影響
内部不正が企業に与える影響は、現金の着服や商品の横領といった表面的な金銭的被害にとどまらず、損害賠償や信用失墜による取引機会の損失、調査費用やシステム改修費用などのコストなど多岐にわたり発生します。
さらに、事件の影響で離職者が増加したり、新たな人材確保が困難になるなど、人的資源の面でも深刻な影響を及ぼすことがあります。
具体的な内部不正の手口・事例
内部不正の主な手口や、近年起こった実際の事例を紹介します。
典型的な不正の手口
内部不正は、主に「情報漏洩」「資産の窃取」「不正アクセス」の3つのパターンがあります。
▼情報漏洩
企業の機密情報や顧客情報の漏洩は、発生頻度の高い内部不正の一つです。自席のパソコンから個人所有のUSBメモリへのコピー、営業資料の無断プリントアウトといった形で行われます。また、スマートフォンでの画面撮影や、私用メールアドレスへの送信、オンラインストレージへのアップロード、さらにはSNSでの情報公開といった手口もあります。
▼資産の窃取
現金の着服に加え、架空取引による資金移動や経費の水増し請求をする手口が見られます。また、在庫商品の無断持ち出し、備品の私物化や廃棄物として偽装した横領など、物理的な資産の流出も、深刻な問題です。
▼不正アクセス
システムへの不正アクセスは、デジタル化が進む現代において特に注意が必要です。他者のIDパスワードを悪用したり、退職者アカウントを継続使用するなどシステム管理者権限の乱用による、データの改ざんといったケースも発生しています。
過去事例から見る内部不正の手口と対策
ここでは、実際に発生した内部不正の代表的な事例を紹介し、その特徴と対策を解説します。
▼大手金融機関の不正出金事件(2024年)
2024年に発覚した大手金融機関での事件では、銀行員がスペアキーを使用して顧客の貸金庫から現金を不正に持ち出し、約4年半にわたって累計で十数億円の被害が発生しました。
発生要因としては、スペアキーの管理体制の不備、拠点内や本部等による牽制・モニタリングの不十分さが指摘されました。この事件を受けて同金融機関では、重要な鍵の管理方法の見直し、貸金庫への入退室・開閉状況の管理強化、貸金庫内への防犯カメラ増設などが実施されています。
▼大手通信会社の顧客情報流出事件(2023年)
2023年には、大手通信会社の子会社で働いていた元派遣社員が、システムの管理アカウントを使用してサーバーにアクセスし、約900万件もの顧客情報を流出させる事件が発生しました。
この事件の主な発生要因として、以下の4点が挙げられています。
- 保守作業端末にデータのダウンロードが可能な状態だった
- 保守作業端末に外部記録媒体を接続できる状態だった
- セキュリティリスクの高い行動をリアルタイムに検知できなかった
- 各種ログの定期的なチェックが不十分だった
これを受けて同社では、保守作業端末へのダウンロード制限、外部記録媒体の接続制限、セキュリティリスクの高い行動の検知・アラーム通知システムの導入、定期的なログチェックの徹底などの対策を講じています。
これらの事例から学べることは、内部不正は単一の要因ではなく、複数の脆弱性が重なって発生することが明らかです。そのため、対策も物理的なセキュリティ、システム面でのセキュリティ、運用面でのチェック体制など、複数の層で実施する必要があります。
次の項目では、このような内部不正を防ぐための基本的な考え方について解説していきます。
内部不正対策の基本的な考え方
アメリカの犯罪学者ドナルド・クレッシーは、次の3つの要素が揃うと不正行為が起こりやすいと指摘しています。
- 動機:不正を働きたくなる要因のこと。借金を抱えている、売上のノルマによるプレッシャー、職場の待遇に不満があるなど
- 機会:不正を実行できる状況のこと。監視体制が甘い、業務が属人化している、上長の目が届かないなど
- 正当化:不正行為を正当化するための理由。会社や社会が悪い、みんなやっているからなど
不正行為は、これらの「動機」「機会」「正当化」の3つの要素が揃うと起こりやすくなるため、対策としてはこれらを低減できるような不正防止策を講じることが大切です。
IPAの「組織における内部不正防止ガイドライン」では、この3つの要素に対応する形で、「内部不正防止の基本5原則」を次のように策定しています。
| 犯行を難しくする(やりにくくする):対策を強化することで犯罪行為を難しくする 捕まるリスクを高める(やると見つかる):管理や監視を強化することで捕まるリスクを高める 犯行の見返りを減らす(割に合わない):標的を隠す/排除する、利益を得にくくすることで犯行を防ぐ 犯行の誘因を減らす(その気にさせない):犯罪を行う気持ちにさせないことで犯行を抑止する 犯罪の弁明をさせない(言い訳させない):犯行者による自らの行為の正当化理由を排除する |
これらの原則を踏まえ、次章では具体的な対策について、「予防」「発見」「事後対応」の3つの段階に分けて解説します。
予防・発見・事後対応から見る内部不正対策のポイント
内部不正対策は、「予防的対策」「発見のための対策」「事後対応の準備」の3つの段階で考えることが重要です。それぞれの段階で適切な措置を講じることで、より効果的な対策が可能となります。
予防的対策
内部不正を未然に防ぐためには、システムによる制限と人による管理の両方が重要です。
アクセス権限の管理では、情報システムへのアクセスと同様に、オフィスのエリアごとに適切な入室制限を設けます。例えば、経理部門には経理部の従業員のみが入室できるようにするなど、業務に必要な範囲での権限付与を徹底します。
| <アクセス権限管理のポイント> ・必要最小限の権限付与 ・定期的な権限の見直し ・異動・退職時の速やかな権限削除 ・入退室管理システムによる立入制限 |
業務の分担と相互チェックも重要な予防策です。ひとりの従業員に重要な業務や権限が集中すると、不正のリスクが高まるためです。例えば、在庫管理と出納業務を同じ人が担当していると、不正な持ち出しが発生しても発見が遅れる可能性があります。重要な業務は複数人で担当し、お互いのチェックが働く仕組みを作ることが大切です。
| <業務の分担と相互チェックのポイント> ・重要な業務は1人に任せきりにしない ・複数の担当者でチェックし合う体制づくり ・定期的な担当者の交代 ・重要エリアの監視カメラによる記録 |
在庫管理においては、定期的な棚卸が欠かせません。特に、在庫の出し入れが多い倉庫や、高額な機器を保管している場所では、入退室記録と合わせて確認することで、不正の早期発見が可能になります。
| <在庫管理のポイント> ・資産の定期的な確認 ・差異の即時把握と原因究明 ・在庫管理システムの活用 ・倉庫や重要物品保管場所の入退室記録 |
従業員教育も重要な予防策の一つです。定期的なコンプライアンス研修を通じて、の具体的な事例や発生原因、その結果として企業と従業員双方が被る深刻な影響について学ぶことで、従業員の危機管理能力が高まります。このような理解が深まることで、「これは不正行為かもしれない」という判断力が養われ、自身の行動を見直すきっかけになるとともに、周囲の不審な動きにも気づきやすくなるため、結果として組織全体での不正の抑止効果が期待できます。
| <従業員教育のポイント> ・コンプライアンス研修の定期開催 ・具体的な事例を用いた啓発活動 ・相談窓口の設置と周知 ・セキュリティ設備の目的と運用ルールの周知 |
発見のための対策
内部不正の兆候を早期に発見するためには、日常的な確認と定期的なチェックの両方が欠かせません。
定期的なモニタリングでは、システムログや入退室記録、監視カメラの映像など、様々な記録を確認します。これにより、不審な動きを早期に発見できます。ただし、プライバシーに配慮し、必要な範囲での確認にとどめることが重要です。
| <モニタリングのポイント> ・アクセスログの分析 ・入退室記録の定期的な確認 ・監視カメラ映像の定期確認 |
また、従業員が不正や疑わしい行為を発見した際に、安心して報告できる内部通報制度の整備も重要です。通報者の保護を明確にし、外部の窓口を設置するなど、利用しやすい制度づくりを心がけましょう。
| <内部通報制度のポイント> ・匿名性の確保 ・通報者保護の明確化 ・外部窓口の設置 |
事後対応の準備
不正が発覚した際の混乱を最小限に抑えるためには、事前の準備が欠かせません。内部不正が発覚した場合、まず必要なのは事実関係の確認です。入退室記録や監視カメラの映像は、不正の実態を把握する上で重要な証拠となります。これらの記録を適切に保存し、必要に応じて提出できるよう、手順を定めておくことが大切です。
また、発覚した不正の手口や原因を分析し、同様の不正を防ぐための対策を講じることも重要です。例えば、死角となっている場所への監視カメラの増設や、入退室管理の権限設定の見直しなどが考えられます。
| <事後対応準備のポイント> ・インシデント対応手順の文書化 ・証拠保全の方法の確立(入退室記録、カメラ映像の保存) ・関係機関への報告体制の整備 ・再発防止策の検討プロセスの確立 ・セキュリティ設備の見直しと強化計画の策定 |
物理的セキュリティ対策の重要性
物理的セキュリティとは、建物や部屋への入り口を適切に管理し、重要な情報や資産を保護する対策のことです。情報システムのセキュリティだけでなく、実際の建物や部屋のセキュリティを確保することで、より確実な内部不正対策が実現できます。
例えば、オフィスビルの場合、1階のエントランスで入館チェック、フロアごとの認証、さらにサーバールームなどの重要な部屋では暗証番号や生体認証など多段階の認証が効果的です。不正行為が起こりやすい3つの要素(動機・機会・正当化)のうち、これにより不正行為の「機会」を与えないようにします。
物理的セキュリティを実現するための手段としては下記の方法が挙げられます。
入退室管理システム
社員証やICカードを使って、誰がいつどこに入ったかを記録・管理するシステムです。このシステムにより、許可された人だけが入室でき、かつ、誰がいつ入室したかの記録が残ります。
入退室管理のタイプや選び方は以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
また、入退室管理システムの導入に必要なノウハウをまとめた資料も下記よりダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。
監視カメラ
監視カメラシステムで重要な場所や死角になりやすい場所を録画することで、不正行為の抑止と証拠の記録ができます。
防犯カメラの効果や選び方は以下の記事でも詳しく解説しています。
また、監視カメラシステムの導入に必要なノウハウをまとめた資料は下記よりダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。
セキュリティゲート
入退室管理システムはICカードや暗証番号などを使って入退室の記録を管理することができますが、そこにセキュリティゲートを連携させることで物理的にアクセスを制御できるので、より確実な入退室管理が可能になります。例えば、「共連れ」(権限を持つ入室者の後について不正に入室すること)を防止できます。
防犯センサー
監視カメラと組み合わせることで、不正侵入の検知と証拠の記録が可能です。センサーが反応した際に自動的に録画を開始したり、警報を発したりすることができます。
これらの対策は、企業の規模や重要度に応じて、必要なものを選択し組み合わせることが重要です。また、導入後も定期的な点検や運用ルールの見直しを行い、実効性を確保するようにしましょう。
内部不正対策に効果的なセキュアのソリューション
これまで解説してきた内部不正対策。その中でも特に重要な「入退室管理」と「監視カメラ」について、株式会社セキュアでは2つのシステムソリューションを提供しています。いずれも、企業の規模や用途に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。
入退室管理ソリューションサービス「SECURE AC」
セキュアが提供する「SECURE AC」は、顔認証技術、ICカード、二次元バーコードなどを組み合わせて使用することができる入退室管理システムです。なりすましを防ぎ、確実な本人確認ができる点が特徴で、顔認証システムとしては3年連続で導入実績No.1を達成しています。
<SECURE ACの主な特徴>
- 確実な本人確認:顔認証で入退室を管理し、他人による代理打刻を防止
- 二重のセキュリティ:2人のユーザーが一定時間内に認証する「ダブル認証、ツーパーソンルール」を設定可能
- 詳細な記録管理:誰が、いつ、どこに入退室したかを正確に記録
- 柔軟なアクセス制御:フロアごとのエレベーター利用制限なども設定可能
- 緊急時対応:火災報知器や警備システムと連動した自動解錠が可能
- 他システムとの連携:勤怠管理や在室管理、受付システムとの統合が可能
詳しくは以下のページで詳しく紹介しています。
セキュアの入退室管理システム「SECURE AC」の詳細はこちら
監視カメラシステム「SECURE VS」
セキュアの監視カメラシステム「SECURE VS」は、豊富な種類のカメラを取り揃え、お客様のニーズに合った最適なプランを提案します。
<SECURE VSの主な特徴>
- アナログ・ネットワークともに高い解像度のカメラをラインナップ
- 魚眼レンズである360°カメラ映像の歪み補正機能
- レコーダーの障害発生時にmicroSDカードや予備レコーダーへの録画が自動的に開始される「スマートフェイルオーバー」機能
詳しくは以下のページで詳しく紹介しています。
セキュアの監視カメラシステム「SECURE VS」の詳細はこちら
セキュアでは、これらのソリューションについて、導入の提案から設計・施工、そして導入後の保守まで、一貫したサポート体制を整えています。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:入退室管理と監視カメラで内部不正させない環境を作ろう
本記事では、内部不正の基礎知識から具体的な対策、そして物理的セキュリティの重要性について解説してきました。
今回紹介したものは、あくまでも手段の一部です。事例からみても、内部不正は複数の脆弱性が重なって発生しています。そのため、内部不正のリスクを下げるためには「人による対策」と「システムによる対策」をおこなうことが重要です。例えば、従業員教育やコンプライアンス意識の向上といった人による対策に加えて、入退室管理システムや監視カメラによる物理的なセキュリティ対策を導入することで、より確実な内部不正の防止が可能になります。既存の入退室管理システムや監視カメラを定期的に見直し、最新の脅威に備えましょう。
セキュアでは、物理的セキュリティ対策の要となる入退室管理システム「SECURE AC」と、監視カメラシステム「SECURE VS」を提供しています。「SECURE AC」は顔認証、ICカード、二次元バーコードなどを組み合わせた確実な入退室管理を実現し、「SECURE VS」は高解像度カメラや360°映像の歪み補正機能など、さまざまな機能で幅広いニーズに対応します。
内部不正対策でお悩みの方は、豊富な導入実績を持つセキュアの入退室管理・監視カメラシステムをぜひご検討ください。導入のご相談から設計・施工、保守まで一貫してサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

セキュリティマーケター
和田 麗奈
保有資格:防犯設備士
株式会社セキュアに入社後4年間、セキュリティソリューション営業に従事。多岐にわたる業界・業種の課題解決に貢献する。
現在はマーケティングチームに所属し、現場での経験を活かしながら活動中。