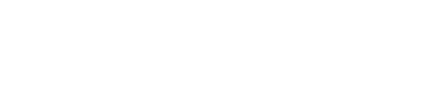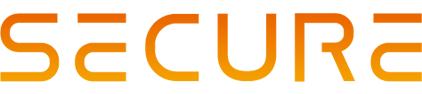ICカードによる入退室管理システム導入完全ガイド!おすすめのケースや注意点、認証方法の比較を解説

企業のセキュリティ対策として、ICカードを活用した入退室管理システムが広く導入されています。
低コストで導入しやすく、既存の社員証や交通系ICカードをそのまま活用できる手軽さが魅力です。一方で、カードの貸し借りや紛失・盗難、管理面における課題も少なくありません。
本記事では、ICカードを活用した入退室管理の仕組みやおすすめのケース、注意点、登録方法、ICカード以外の認証方法の紹介など網羅的に解説します。ICカードでの運用を検討中の方や課題を感じている方が、「他の認証方法とどう違うのか」「導入時に注意すべきポイントは何か」などの疑問を解消できる内容となっていますので、ぜひご覧ください。
なお、株式会社セキュアでは、ICカード・顔認証・二次元バーコード認証などの幅広い認証機能や他社とのシステム連携を含めた「SECURE AC」入退室管理システムを提供しています。
さまざまな業種や課題・環境に適した入退室管理のご提案ができる「SECURE AC」入退室管理システムについての詳細は、下記をクリックのうえ、ご覧ください。
目次
ICカードによる入退室管理システムとは

ICカードによる入退室管理とは、ICカード内に記録された数十桁の数字をカードリーダーが読み取って認証権限の有無を判定する仕組みです。
ICカードによる入退室管理システムによって、特定の場所への入室制限や、部外者の侵入防止、履歴の管理など物理的なセキュリティが構築できます。
なお、入退室管理システムそのものについての詳細や導入方法について下記の記事で解説していますので、ご覧ください。
ICカードの主な種類
ICカードには、主に下記の3種類があります。
| 種類 | 特長 | 詳細 |
|---|---|---|
| FeliCa(フェリカ) | ・ソニー社が開発している技術方式 ・高いセキュリティ性能 ・通信速度が速い | ・「FeliCa Standard」と「FeliCa Lite-S」があり、どちらも入退室管理に使用できる ・「Pasmo」や「Suica」もFeliCaに分類される |
| Mifare(マイフェア) | ・ICカードの国際通信規格(ISO14443)として標準化され、世界的に最も多く普及している ・内部的にIDm番号を所有している | ・Mifare standard 1K ・Mifare standard 4K ・MifareUL(マイフェアウルトラライト) ・MifareDESfire(マイフェアデスファイヤー) ・MifarePlus (マイフェアプラス)などがある |
| EMカード | ・水や金属の影響を比較的受けにくい ・以前は日本でも入退室管理システムのカードとして使用されることが多かった | 高速通信、高セキュリティの「MifareDESfire」や「MifarePlus」は稀に金融機関や個人情報を取り扱っている企業で使用する場合がある |
ICカードによっては入退室管理システムのカードリーダー(※)に対応していない場合があります。既にICカードを自社で使用している場合、そのカードが入退室管理システムのカードリーダーとの互換性があるか、対応規格の確認が必要です。
(※)カードリーダー……ICカードに記録されたデータを読み取るための装置のこと
ICカードの登録方法
ICカードの登録方法には、主に「一括登録」と「個人登録」の2種類があります。
下記にそれぞれの登録方法をまとめました。
一括登録
大量のICカードの番号をまとめたCSVデータの用意があれば、短時間で一括でのアップロードが可能です。誤入力を防ぐためにも利用者情報を事前にCSVなどに情報を整理しておきましょう。
【一括登録の手順】
| ①カード情報の準備 | ICカードには、内部のICチップにカード番号が記録されているため、事前に販売元や管理システムで確認し、適切なデータを用意する |
|---|---|
| ②カードの使用者を決定する | 利用者ごとに、どのICカードを割り当てるかを決める |
| ③リストにまとめる | 利用者の氏名・部署・カード番号などをCSVファイルに整理する |
| ④情報をインポート | 管理システムにデータをアップロードし、一括登録を完了する |
個人登録
個人登録は、少人数や追加登録などを手動で登録する方法です。慣れれば1分ほどで終わる作業なので、少人数なら簡単で柔軟な対応が可能です。
導入する製品によっては、PCを使用せず、設置したカードリーダーで個別に登録が必要な場合があります。
個人登録は、主に下記の3ステップで実施します。
【一個人登録の手順】
| ①PCで利用者の登録 | 利用者情報を管理システムに入力する |
|---|---|
| ②PCにカード登録機を接続 | USB接続やネットワーク接続などの種類がある |
| ③登録機でカードを読み込ませ登録 | 利用者ごとに登録機でICカードを読み取り、システムに登録する |
とはいえ、初めて導入される場合は「どちらの方法が良いのか」「どんな手順で登録すれば良いのか」と、悩まれることもあるかもしれません。
株式会社セキュアが提供する入退室管理ソリューションサービスは、自社コールセンターの設置や全国に広がるサポートネットワークにより、導入後のサポートも充実しています。
お客様から「フットワークが軽い」と喜びの言葉もいただいているセキュアの入退室管理ソリューションサービスについて関心のある方は、下記からお気軽にお問い合わせください。
入退室管理にICカードがおすすめのケース4選

本章では、ICカードによる入退室管理が特に適している4つのケースをご紹介します。
ケース1.小~中規模オフィスでコストを抑えてセキュリティを導入したい
一つ目のおすすめケースは、コストを極力抑えて入退室管理のセキュリティを向上したい中小企業です。
ICカードでの入退室管理は、リーダーとカードを設置するだけで運用が開始できる他、下記のような観点からも、数名〜30名ほどの規模ではICカードによるセキュリティがおすすめです。
- 人数が少ない分、カードを失くすリスクや使用頻度が低い
- 厳密なセキュリティ要件がない場合、ICカードによる入退管理で十分対応可能
オフィスの入退室管理にICカードを導入すると、鍵の交換や物理鍵の管理が不要になり、長期的なコスト削減につながります。
ケース2.セキュリティレベルを上げたいが、鍵の複製が不安
ICカードでの入退室管理は、認証情報がデジタル化されており、物理鍵のように簡単に複製される心配がないのが大きな特長です。
そのため、鍵の複製や不正利用といったリスクを避けたい企業にとっても、ICカードを導入することで被害リスクが格段に減り、運用管理が効率化された事例が多数あります。
下記の記事では、セキュアの入退室管理システムでICカードを採用し、鍵の運用効率化を図った企業の事例を紹介しているので、関心のある方はご覧ください。
事例:ICカードの採用で、運用管理を効率化|株式会社レーベン様
ケース3.既存のICカードを有効活用したい
ICカードでの入退室管理は、社員証や交通系ICカードなど、既に社員が持っているカードをそのまま活用できる場合があります。
新たなカードを発行する手間やコストを省きながら、スムーズにセキュリティ管理を始めたい企業にぴったりです。すでに勤怠管理や複合機認証などでICカードを活用している企業は、下記のような点でもおすすめです。
- 入退室と勤怠のデータをまとめて管理できる
- 追加の認証方法を導入する場合でも、社員証を併用するため、ICカード型の入退管理システムとの相性が良い
もし、複数のカードを管理しているのであれば「カードレスでの運用」も視野に入れ、生体認証で連携を検討するのも一つの方法です。
ケース4.使い慣れた仕組みでスムーズに運用したい
ICカードは、今では多くの人が「Suica」や「PASMO」などの交通系ICや社員証などで慣れ親しんでおり抵抗感なく利用できます。
システムに不慣れな社員や高齢の従業員が多い職場など、すぐに使い方を理解でき、抵抗なく導入したい企業におすすめです。
初期の研修やマニュアル作成の負担も軽く、現場に負荷をかけずに短期間で現場へ定着するのが大きな利点です。
入退室管理にICカードを使う3つの注意点

次に、入退室管理にICカードを使う3つの注意点を紹介します。
注意点1.カードの貸し借りによる不正利用のリスク
ICカードは物理鍵よりも複製されにくいものの、従業員間での貸し借りは容易にできてしまうため、下記のようなリスクがあります。
- 権限のない者が機密エリアに侵入
- 入退室記録の正確性が損なわれるおそれ
対策として、貸与ルールの明確化や、顔認証やPINコードとの併用である「多要素認証」を取り入れて、不正利用を防ぐのがおすすめです。複数の要素を組み合わせることで、セキュリティの強度が大きく向上します。
| 【多要素認証とは】 セキュリティ強化のために、2つ以上の異なる要素を同時に使用し、ユーザを認証する方法 |
多要素認証の主な3つの要素は下記のとおりです。
| 知識要素(ユーザーのみが知っている情報による認証) | パスワード・PINコード・秘密の質問など |
|---|---|
| 所有要素(ユーザーのみが所有している物による認証) | ICカード・スマートフォン・セキュリティトークンなど |
| 生体要素(ユーザー自身の身体的な特徴による認証) | 顔認証・指紋認証・虹彩認証・声紋認証など |
なお、複数の認証方法でセキュリティの強化を図るなら株式会社セキュアが提供する「SECURE AC」入退室管理システムがおすすめです。機密情報の漏洩を防ぐための入室制限として、「カード」+「顔認証」など複数要素を組み合わせた認証の設定が可能です。
さらに、業務のDX化に合わせてさまざまなシステムとの連携も可能な「SECURE AC」入退室管理システムについては、下記からご覧ください。
注意点2.ICカードの紛失・盗難リスク
ICカードを紛失したり盗まれたりした場合、第三者に不正利用されるリスクが一気に高まります。
特に、個人情報や機密情報が記録されたICカードが悪意のある第三者に渡った場合、情報漏洩につながるおそれもあります。
対策として、前述した「多要素認証」で不正利用を防ぎましょう。また、紛失時の迅速な無効化手続きを整備し、管理体制を強化するのもおすすめです。
注意点3.ICカードの管理が煩雑
従業員数が多い企業や、頻繁な入退室管理が必要な施設では、ICカードの管理が煩雑になる場合があります。
例えば、新規発行、紛失・盗難時の再発行、部署異動や退職時の権限変更などが発生し、管理者の負担が大きくなることが考えられます。
また下記のようなトラブルを防ぐため、ICカードの取り扱いにも配慮が必要です。
| ICカードを重ねての認証は避ける | ・磁気が弱くなり、反応が悪くなる ・2枚以上を持ち歩く際は、間にセパレータ(仕切り)をはさむ |
|---|---|
| 磁気を発するものの近くでの保管・使用は避ける | ・磁気を発するものの近くに保管したり、一緒に使用したりすると、データが破損する恐れがある ・スマートフォンや電子レンジなどの近くに置かない |
| ICカードの適切な管理と定期的なメンテナンスをおこなう | ・ICカードは精密機器であり、衝撃や水濡れに弱いという特徴がある ・丁寧に扱い、定期的に清掃などのメンテナンスを行う ・ICカードリーダーも定期的に清掃し、正常に動作することを確認する |
対策として、クラウド型の入退室管理システムを導入し、ICカードの登録・権限変更を一元管理することで、業務負担を軽減するのがおすすめです。
なお、ICカードのリスク自体をなくしたい場合は、カードレス運用が可能な顔認証など生体認証の導入も検討してみましょう。生体認証についての詳細は、下記の記事をご覧ください。
ICカードを入退室管理に導入する際の4ステップ

ICカードを入退室管理に導入する際のステップを、4段階で紹介します。
ステップ1.入退室管理の運用ルールを決める
まず、「誰が」「いつ」「どこに」アクセスできるのか、基本的なルールを明確にしましょう。
例えば、よくあるルールは下記のとおりです。
- 部署ごとにアクセス権限を設定する
- 深夜・休日などの時間帯で制限をかける
- 管理エリアを「一般エリア」「制限エリア」「機密エリア」に分類する
アクセス権限を細かく設定することで、無駄な立ち入りを防ぎ、セキュリティレベルを段階的に高められます。
ステップ2.必要なICカードの種類とシステムを選ぶ
次は、使用するICカードの種類とシステムの選定です。
既存のICカードを活用するか、新たに発行するかを検討します。必要に応じて、利用するICカードの種類(MIFARE、FeliCaなど)を決定しましょう。
また認証方法や管理機能など、必要なシステム要件を洗い出しておきます。事前に要件を整理しておくと、後から「機能が足りない」「連携できない」などのトラブルを防ぐことができます。
ステップ3.設置場所を決定し、適切な機器を用意する
システムとカードの方向性が決まったら、次は設置場所と機器の選定です。
オフィスの出入り口やサーバールームなどの重要エリアに、カードリーダーを設置します。その際、扉の種類や材質に合わせて、電気錠やオートロックなどの機器を選定するようにしましょう。
設置環境に合った機器を正しく選定することで、システムの安定稼働やトラブルの予防にもつながるため、専門業者への相談がおすすめです。
ステップ4.ICカードの登録とアクセス権限を設定する
最後に、ICカードと社員情報を紐づけ、個別にアクセス権限を設定します。
従業員情報(氏名・所属など)を管理システムに登録し、ICカードと紐付けます。部署や役職に応じて、適切なアクセス権限も設定しましょう。
ICカードによる入退室管理は、企業ごとに異なる要件や環境に適した設計が求められるため、より適切なシステムを構築するには導入前に専門家へ相談するのがおすすめです。
なお、株式会社セキュアでは、豊富な導入実績をもとにお客様に適したシステムをご提案させていただきます。下記からお気軽にお問い合わせください。
ICカード以外の認証方法

ICカード以外にも「テンキー」や「顔認証」など入退室の際の認証方法は多くあります。
本章では、数ある認証方法から代表的な3つをご紹介します。
認証1.顔認証
顔認証は、「顔の情報」を読み取り、個人を識別できる認証方法です。主に、下記のような特徴と注意点があります。
| 特徴 | ・物理的なカギやカードを持ったり、パスワードを設定する必要がない ・認証速度も早い ・気温や湿度など環境要因の変化や顔の汚れ、汗などの付着物の影響を受けにくい |
|---|---|
| 注意点 | ・ICカード型に比べると価格は高い |
例えば、食品工場のように衛生管理が求められる現場では、非接触の顔認証が衛生リスクの低減とセキュリティ強化の両面で有効なソリューションとなり得ます。
カード紛失のリスクの解消と運用の負担軽減の実現に向けて、セキュアの生体認証を導入した企業様の事例を下記で紹介します。信頼が重要となる金融機関向けのシステム開発企業様において、顔認証の導入によって顧客の安心獲得にもつなげた事例となっておりますので、ぜひご覧ください。
導入事例|顔と指紋のハイブリッド生体認証で金融システム開発の安全を守る|株式会社リボルブ・シス様
認証2.指紋認証
指紋認証とは、隆線と呼ばれる指表面の突起の特徴を読み取り、照合を行う認証方法です。指紋認証の主な特徴と注意点は、下記のとおりです。
| 特徴 | ・生体認証の中では安価で導入しやすい ・手袋を着用したまま認証出来るものもある |
|---|---|
| 注意点 | ・指の細い女性の方や指紋がすり減っている方、ケガをしている方は認証や登録に苦戦する場合がある ・指が乾燥した状態では認証しづらく、環境に影響を受ける場合がある ・偽造指紋による突破の可能性がゼロではない |
コストを抑えて生体認証を導入したい場合に適していますが、環境やユーザーによっては認証精度に注意が必要です。
異物持ち込みのリスクを最小限に抑えたい環境では、指紋認証を導入することでICカードを不要にし、より厳格な入退室管理を実現できます。
下記の記事では、多拠点の一括管理に指紋認証を導入した事例を紹介しているのでご覧ください。
導入事例|指紋認証で14拠点の一括管理を実現|株式会社エスプール様
認証3.静脈認証
静脈認証とは、指や手の内部にある血中のヘモグロビンを赤外線で読み取り、個人を識別する認証方法です。主な特徴と注意点を、下記に挙げました。
| 特徴 | ・指紋や顔と異なり、表面の汚れや傷の影響を受けにくい ・非接触型のシステムもあり、衛生的に使用できる |
|---|---|
| 注意点 | ・導入コストが比較的高く、特に高精度な装置は費用がかかる ・季節や外部からの影響を受けやすく、認証精度が環境に左右されやすい |
高いセキュリティが求められる環境に適していますが、指輪による指への圧迫で認証がしづらくなるケースもあります。
入退室管理のセキュリティ強化ならセキュアの「SECURE AC」

セキュリティソリューションの導入社数11,000社を超える株式会社セキュアでは、カードリーダーや顔認証、2次元コード認証などの幅広い認証機能や他社とのシステム連携を含めたセキュリティソリューション「SECURE AC」入退室管理システムを提供しています。
「カード」+「顔認証」の2重認証が設定でき、正確な本人確認が可能です。本章では、「SECURE AC」入退室管理システムの主な特徴を3つ紹介します。
特徴1.正確なログで、「誰が・いつ・どこにいたのか」を把握できる
セキュアの入退室管理システムは、正確な入退室ログを取得できるため、「誰が・いつ・どこにいたのか」などの情報を明確に把握できます。
入退室履歴の正確なログの他にも、不審な行動の追跡やセキュリティ監査の強化も可能です。正確なログがあれば、迅速な原因究明や対応も可能となります。
なりすましや貸し借りによる不正利用を防ぎ、よりセキュリティを強化したい企業にもおすすめです。
特徴2.働き方改革・業務のDX化に合わせた多様なシステム連携が可能
勤怠管理システムや警備システムなどと連携できるため、業務の効率化や従業員の負担軽減に貢献します。
例えば、ICカードで入退室と同時に出勤・退勤を記録したり、顔認証と連動した出勤管理を実施したりすることで、管理業務の省力化が可能です。DXの推進を考える企業にとって、柔軟な連携性は大きなメリットの一つです。
特徴3.複数拠点の一括管理が可能
本社・支社・工場など、離れた複数拠点の入退室を一元管理できるため、セキュリティレベルの統一が図れます。
拠点ごとにバラバラな管理体制になっていた場合でも、「SECURE AC」入退室管理システムを導入すれば、一つの管理画面で全体を把握できるようになり、ガバナンスの強化や情報管理の効率化に寄与します。
顔・指紋・カード・テンキーと用途に合わせた多様な認証デバイスを取り揃えて、お客様の課題に柔軟に対応できるセキュアの入退室管理システムについての詳細は、下記からご覧ください。
ICカードを活用した入退室管理に関するよくある3つのQ&A

最後に、ICカードを活用した入退室管理に関するよくある3つの疑問にお答えします。
気になるものから、チェックしてみてください。
Q1.社員証をICカードとして使用することは可能ですか?
社員証を入退室管理のICカードとして 使用することは可能です。
ただし、MIFAREやFeliCaなど、ICカード規格が対応しているか、事前にシステムとの互換性を確認しましょう。社員証にICチップを搭載すれば、入館管理と勤怠管理を統一することもできます。
なお、企業によっては、入居するビル側で共通の入館カードが発行されているケースもあります。ビルで使用するICカードの規格が企業のシステムと異なる場合、社員証との統合が難しい点にも留意しておきましょう。
あらかじめ認証確認用のデモ機などで、動作確認をしておくと安心です。
Q2.システムの導入にかかるコストはどの程度ですか?
ICカードリーダーの価格は、1台あたり 2万円〜数十万円が一般的です。(性能や認証機能により変動する)
クラウド型は月額費用制で、オンプレミス型は初期導入費用が高めの傾向があります。その他、ICカード発行費用(1枚数百円〜)やメンテナンス費用、システム更新費用などがかかります。
入退室管理システムの相場を詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてご覧ください。
Q3.カードリーダーに種類はありますか?
ICカードリーダーには、主に「接触型」と「非接触型」の2種類があります。主な特徴は下記のとおりです。
| 接触型 | ICカードをリーダーに挿入して読み取るタイプで、主にクレジットカードやキャッシュカードなどに利用されている |
|---|---|
| 非接触型 | ICカードをリーダーにかざすだけで読み取るタイプで、交通系ICカードや社員証などに利用されている |
用途や利用シーンに合わせて、適切なカードリーダーを選択しましょう。
入退室管理にはICカードと他の認証を組み合わせてさらなるセキュリティ強化を図ろう

ICカードによる入退室管理は、社員証や交通系カードを活用でき、低コストで導入しやすい点が魅力です。
一方、カードの貸し借りや紛失などのリスクもあるため、顔認証や指紋認証と併用する「多要素認証」を検討するとさらに安全性が高まります。
ICカードと他の認証を組み合わせて運用し、より強固なセキュリティ体制を構築していきましょう。
なお、「社員証だけで大丈夫か?」「複数拠点を一括管理できるシステムはないか?」といった疑問や不安がある場合は、ぜひ株式会社セキュアの「SECURE AC」入退室管理システムをご検討ください。オンプレミスとクラウドの両方式に対応しており、幅広い業種・規模に適したセキュリティソリューションをご提案いたします。まずは、お気軽に下記からお問い合わせください。

セキュリティマーケター
和田 麗奈
保有資格:防犯設備士
株式会社セキュアに入社後4年間、セキュリティソリューション営業に従事。多岐にわたる業界・業種の課題解決に貢献する。
現在はマーケティングチームに所属し、現場での経験を活かしながら活動中。